アトリエシリーズは興味あるけど、今が何作目で何から始めればいいのか?何が面白いのかわからないように色々まとめました。
アトリエシリーズ初心者ガイド
アトリエシリーズは、錬金術(れんきんじゅつ)をテーマにしたRPGシリーズです。1997年発売の初代『マリーのアトリエ』から始まり、2025年発売の最新作『ユミアのアトリエ』まで、25年以上にわたり多数の作品が展開されています。各作品で新たな主人公と物語が描かれますが、共通して素材集めや**調合(ちょうごう)といった要素が楽しめるのが特徴です。また、作品はいくつかのシリーズ(世界観)**ごとに分かれており、シリーズ間でストーリーの直接的な繋がりはないため、気になる作品から始めても大丈夫です。この記事では、アトリエシリーズ未経験の方に向けて、全作品のシリーズ分類や時系列、キャラクターのつながり、基本システム、そして初心者におすすめのタイトルやプレイ順のヒントをご紹介します。
アトリエシリーズの作品一覧とシリーズ分類
アトリエシリーズは現在までに本編だけで25作以上が発売されており、いくつかの世界・年代ごとのサブシリーズに分類できます。以下に主なシリーズと対応作品をまとめ、その**作中年代(時系列)**も補足します。
ザールブルグ(Salburg)シリーズ – A1〜A3作目
- 『マリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士~』 (1997年発売) – 記念すべきシリーズ第1作。若き錬金術士マリーがアカデミーの卒業試験に挑みます。期限内(5年)に成果を出すという時間制限付きのゲーム進行が特徴です。
- 『エリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士2~』 (1998年発売) – マリーの後輩エリーが主人公の続編で、物語の舞台はマリーの物語から6年後です。マリーがエリーの人生の転機を与えた縁で、エリーは同じアカデミーに入学し錬金術を学びます。
- 『リリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士3~』 (2001年発売) – 錬金術士リリーがザールブルグで初めてアカデミーを作ろうと奮闘する物語。シリーズ3作目ですが時系列的には前日譚で、マリーより20年前の世界が描かれます。過去の時代設定のため、若き日のザールブルグ王など初期作に繋がるエピソードが登場します。
※ザールブルグシリーズはすべて同一の王国(ザールブルグ王国)が舞台で、主要キャラクターも一部共通しています。例えばマリーとエリーは師弟のような関係で、エリーの物語には成長したマリーも登場します。
グラムナート(Gramnad)シリーズ – A4〜A5作目
- 『ユーディーのアトリエ ~グラムナートの錬金術士~』 (2002年発売、海外名Atelier Judie) – 天才錬金術士ユーディット(Judie)が主人公。ある調合の失敗で200年後の未来にタイムスリップしてしまい、元の時代に戻る方法を探すというユニークなストーリーです。
- 『ヴィオラートのアトリエ ~グラムナートの錬金術士2~』 (2003年発売) – 村娘ヴィオラート(Viorate)が主人公。家族が引っ越すのを嫌がった彼女は、自分の店(アトリエ)を開いて村に残ることを決意します。両親が「数年後に様子を見に戻る」と告げて去るところから物語が始まり、数年間でお店を繁盛させることが目標です。
※グラムナートシリーズはザールブルグシリーズと同じ世界の別地方を舞台にしています。ザールブルグ地方から遠く離れたグラムナート地方が舞台で、一部ザールブルグシリーズのキャラクターがゲスト登場する場面もあります。ストーリー上の直接的繋がりは薄いですが、共通の時間軸に存在する世界観です。
イリス(Iris)シリーズ – A6〜A8作目
- 『イリスのアトリエ エターナルマナ』 (2004年発売) – 初の本格的ファンタジーRPG色が強いアトリエで、主人公クレインと剣士リータが世界を冒険する物語です。シリーズ初の海外展開となり、西洋のRPGファンにもシリーズを知らしめた作品でもあります。錬金術は登場しますが物語上は戦闘と冒険寄りで、アイテム作成は簡略化されています。
- 『イリスのアトリエ エターナルマナ2 (イリスのアトリエ2 ~ゼベルアークの錬金術士~)』 (2005年発売) – イリスシリーズ2作目ですが、物語上は**前作の前日譚(プリクエル)**に当たります。主人公はフェルトとヴァイスの二人で、異変により崩壊の危機に瀕した世界エデンを救うための冒険に出ます。
- 『イリスのアトリエ グランファンタズム』 (2006年発売) – イリスシリーズ3作目ですが、前2作とは直接繋がらない独立したストーリーです(タイトルに「イリス」とありますが、世界設定は一新されています)。若き錬金術士イリス・フォートナーと仲間たちが「八つの夢の書」を巡る冒険を繰り広げます。
※イリスシリーズは、それまでのアトリエとは大きく趣向が異なり、戦闘やストーリー重視の王道RPG寄りの作風です。錬金術でアイテムを作るシステム自体はありますが、アイテムの特性や品質といった細かな概念はほとんど無く、素材からマナ(精霊力)を取り出して合成するといった簡易的な形式になっています。
マナケミア(Mana Khemia)シリーズ – A9〜A10作目
- 『マナケミア ~学園の錬金術士たち~』 (2007年発売) – 舞台はアルレヴィス錬金学園。伝説の錬金術士を父にもつ青年ヴェインが学園に招かれて入学し、仲間と学園生活を送りつつ成長していく物語です。アイテム調合は学園の課題として物語に組み込まれており、RPGのレベル上げ要素も調合品でキャラクターを強化する形式になっています。
- 『マナケミア2 ~おちた学園と錬金術士たち~』 (2008年発売) – 前作から15年後、経営難に陥ったアルレヴィス学園が舞台。主人公が2人(ラゼとウルリカ)から選択でき、それぞれ異なる視点のストーリーが展開します。両主人公の物語は最終的に合流し、学園に訪れた危機に立ち向かう展開になります。
※マナケミアシリーズは学園ものということもあり、登場人物同士の賑やかな掛け合いやユーモラスなイベントが魅力です。システム的には従来のアトリエの流れを汲んでいますが、戦闘はよりダイナミックになり、錬金術も「レシピ発想」など後のシリーズに通じる新要素が取り入れられています。
アーランド(Arland)シリーズ – A11〜A13, A20作目
- 『ロロナのアトリエ ~アーランドの錬金術士~』 (2009年発売) – 新天地アーランド共和国が舞台。主人公ロロナは廃業寸前のアトリエ(工房)を任され、3年以内に成果を出して閉鎖を回避するため奮闘します。可愛らしいキャラクターと明るい雰囲気で、シリーズの新たな方向性を示した作品です。
- 『トトリのアトリエ ~アーランドの錬金術士2~』 (2010年発売) – ロロナの弟子であるトトリが主人公。師匠ロロナから錬金術を学んだ彼女は、一人前の冒険者になることを目指し旅立ちます。前作から世界が広がり、アーランドの外まで冒険の舞台が広がりました。
- 『メルルのアトリエ ~アーランドの錬金術士3~』 (2011年発売) – アーランドシリーズの集大成。辺境の小国の姫メルルが主人公で、トトリに弟子入りして錬金術を学びます。アーランド国とメルルの国が合併する計画の中、メルルは3年間で領土を発展させ人口を増やすことを課題に、錬金術で国作りに挑戦します。時間制限付きで都市開発をする要素が特徴です。
- 『ルルアのアトリエ ~アーランドの錬金術士4~』 (2019年発売) – 前作から長い時を経て追加された新作で、ロロナの娘ルルアが主人公です。アーランドシリーズの主要キャラが多数再登場し、次世代の物語が描かれます。過去3部作をプレイ済みならニヤリとできる展開もありますが、物語自体はルルアの成長物語として独立しています。
※アーランドシリーズの作中時系列は、ロロナを起点にトトリ、メルルへと約15年の歳月が流れています。ロロナが若手錬金術士だった頃から、トトリが成長し(ロロナはトトリの師匠)、さらにトトリが大人になってメルルの教師役になる頃まで、一貫した時間の流れがあります。そのため各作品には前作主人公が年長者として登場し、人間関係も発展していきます(例:ロロナ → トトリは師弟、トトリ → メルルも師弟の関係で物語に関わります)。ルルアの物語ではロロナが母親という設定で、ロロナやトトリ、他シリーズキャラが年配/伝説的存在として登場します。
黄昏(Dusk)シリーズ – A14〜A16作目
- 『アーシャのアトリエ ~黄昏の大地の錬金術士~』 (2012年発売) – 「黄昏」と呼ばれる世界の終末現象が進行する世界が舞台。若き薬師アーシャは行方不明の妹を探す旅に出ます。3年以内に妹を救う手がかりを掴まないといけないという時間制限がありますが、物語は個人的ながらも心温まる姉妹愛が描かれます。
- 『エスカ&ロジーのアトリエ ~黄昏の空の錬金術士~』 (2013年発売) – 黄昏世界の第2作。錬金術士の少女エスカと青年ロジー、二人の主人公から選んでプレイできます。世界の荒廃が進む中、不思議な遺産が眠るとされる「未開拓の古城」を目指して、二人は役所の調査団として任務に挑みます。前作アーシャの物語から4年後の設定で、世界の謎に迫るストーリー色が強まりました。
- 『シャリーのアトリエ ~黄昏の海の錬金術士~』 (2014年発売) – 黄昏シリーズ完結編。2人の「シャリー」(シャリステラとシャルロッテ)という愛称の少女が主人公で、それぞれ異なる視点の物語が楽しめます。砂漠化が進む世界で水不足に苦しむ人々を救うため奮闘するシャリステラ編と、自分の夢を探すシャルロッテ編が並行して描かれます。エスカ&ロジーの物語からさらに3年後の世界で、シリーズの集大成として黄昏の謎に決着をつける展開になっています。
※黄昏シリーズでは各作品が時間的に連続しており、アーシャ編(3年の物語)→4年後→エスカ&ロジー編(物語期間2年)→3年後→シャリー編…という流れです。そのためキャラクターの再登場も多く、特にエスカとロジーの2人は『シャリー』に成長した姿で再登場します(PS Vita版『シャリーPlus』では前作主人公のエスカ&ロジー、そして初代アーシャまでもパーティ加入し、歴代主人公が集結します)。アーシャの仲間だった登場人物(例えば調査員マリオンなど)もエスカ&ロジーに引き続き登場し、さらに物語に関わるなどシリーズを通じた繋がりが感じられます。
不思議(Mysterious)シリーズ – A17〜A19, A23作目
- 『ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~』 (2015年発売) – 田舎町キルヘンベルに暮らす見習い錬金術士ソフィーが主人公。言葉を話す不思議な本の精霊プラフタと出会い、一人前の錬金術士を目指します。時間制限が廃止され、自由なペースで調合と冒険が楽しめるようになったシリーズ転換点の作品です。
- 『フィリスのアトリエ ~不思議な旅の錬金術士~』 (2016年発売) – 鉱山町育ちの少女フィリスが主人公。ソフィーとの出会いをきっかけに外の世界へ飛び出し、錬金術士になるため各地を巡ります。シリーズ初のオープンワールド風フィールドを採用し、広大な世界を旅する冒険要素が強い作品です。物語序盤でソフィーがフィリスの師匠役として登場し、テント型アトリエを授けてくれます。フィリスは1年以内に各地の錬金術士から推薦状を集め錬金術士試験に合格することが目標で、試験に合格すればその後は時間無制限でプレイ可能になります。
- 『リディー&スールのアトリエ ~不思議な絵画の錬金術士~』 (2017年発売) – 貧乏な双子姉妹リディーとスールが主人公。とある不思議な絵画の中の世界を発見したことから物語が動き出し、一流の錬金術士になることを目指します。前2作の登場人物が多数登場し、ソフィーとその相棒プラフタ、フィリスとその姉リアーネなどが熟練の錬金術士として双子をサポートします。不思議シリーズ三部作の総決算であり、過去作キャラとの交流も見どころです。
- 『ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~』 (2022年発売) – ソフィーシリーズの直接的な続編にあたる作品で、ソフィーとプラフタが新たな夢幻世界で冒険する物語です。時系列上は『ソフィー1』の後、ソフィーがフィリスに出会う前後の物語と推測されますが、舞台が異世界の夢の中で完結しているため他シリーズへの影響はありません。ソフィー1を未プレイでも支障なく楽しめるよう配慮されており、新キャラクターたちとの物語が展開します。
※不思議シリーズは各作品が直接の続編というわけではありませんが同じ世界・時代に位置しており、登場人物の行動範囲が徐々に広がっていくイメージです。ソフィーがフィリスの師となり、フィリスは後にリディー&スールの町で合流して共闘するなど、キャラクター同士の交流関係がシリーズを通じて描かれます。例えばソフィーは初代主人公として各続編にも登場し、フィリスでは先生、リディー&スールでは大先輩として双子を導く役割を果たします。
秘密(Secret)シリーズ – A21〜A24作目
- 『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』 (2019年発売) – 田舎島の少女ライザが主人公。仲間たちと共に島の外の世界で冒険し、錬金術と出会う青春ストーリーです。シリーズ初の等身大の青春ドラマ的な作風と、美しいグラフィックで大ヒットしました。時間制限がなく、採取・戦闘・調合のテンポが非常に良いためシリーズ入門にも人気のタイトルです。
- 『ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~』 (2020年発売) – 前作から3年後、再び主人公ライザの物語が描かれます。ライザは故郷を離れ王都で遺跡探険に挑み、仲間たちとも再会します。ゲームシステムも強化され、水中潜りなど新アクションも追加されました。前作からの続編ではありますが、ストーリー上は新たな目標(遺跡の謎解明)が据えられており、単体でも楽しめる構成です。
- 『ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~』 (2023年発売) – ライザ三部作の完結編。世界各地に突然現れた謎の群島と「東の国」の鍵の伝承を巡り、ライザたちが最後の冒険に出ます。シリーズ初のオープンフィールド的な広大マップが特徴で、ロード無しで広いエリアを探索可能になりました。ライザの成長が大きなテーマとなっており、無印で未熟だった彼女が今作では立派な錬金術士に成長して物語が完結します。
※ライザのアトリエ(秘密シリーズ)はシリーズでも珍しく同じ主人公・同じ仲間たちで三部作が構成されています。ライザ、レント、タオ、クラウディアといった主要キャラクターは3作品すべてに登場し、プレイヤーは彼らの成長を見守る楽しさを味わえます。各作品は独立した冒険譚ですが、キャラ関係は引き継がれるのでできれば発売順にプレイしたほうが物語の感動が深まるでしょう。
その他の本編・新作
- 『アトリエ レスレリアーナ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~』 (2023年配信) – スマートフォン/PC向けの基本無料RPG。極夜に覆われた世界を舞台に、新米錬金術士レスレリアーナが活躍します。シリーズ初の本格的ソーシャルゲームで、いわゆるガチャスタイルの作品です。メインシリーズ作品としてナンバリング上は位置付けられていますが、ゲーム性が大きく異なるため、本記事では詳細は割愛します。
- 『ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~』 (2025年発売) – アトリエシリーズ最新作です。滅びた大陸を舞台に、記憶をテーマとした壮大な物語が描かれます。錬金術が**「禁忌」とされる世界**というこれまでにない設定で、禁じられた錬金術士ユミアが失われた歴史の真実を追い求め旅立つストーリーです。シリーズとしては新たな世界観「追憶(Memories)シリーズ」に当たり、今後の展開にも注目です(本記事執筆時点では発売直後につき詳細な言及は控えます)。
アトリエシリーズに共通する基本システム
アトリエシリーズのゲームシステムは、RPGの冒険要素に加えて錬金術によるアイテム作りが中心になっています。作品ごとに多少の違いはありますが、初心者の方にも共通して押さえておきたい基本要素を説明します。
- 素材集め(採取): 主人公たちは調合の材料となる素材アイテムを集めるため、町の外のフィールドやダンジョンに出かけます。草花を摘んだり鉱石を掘ったり、モンスターを倒してドロップ品を入手したりと、探索と採取が冒険の基本です。採取には季節や天候によって取れるものが変化する場合もあり、シリーズによっては時間経過で素材の品質が劣化することもあります。最新作では広大なフィールドをアクションで駆け回りながら快適に素材集めができるよう進化しています。
- 調合(アルケミー): シリーズの核となるシステムです。集めた素材をアトリエ(工房)で組み合わせ、新しいアイテムを作り出します。回復ポーションや爆弾、武器、防具から料理まで、レシピに沿って様々な道具を錬成できます。作品によって調合システムは工夫が異なり、例えば初期シリーズではシンプルな配合でしたが、グラムナート以降は素材の特性(品質や鮮度)が製品に影響するようになりました。近年の作品ではパズルのように材料をはめ込むミニゲーム式(不思議シリーズ)や、レシピツリーを開拓していく方式(ライザシリーズ)など遊び方が豊富です。初心者の方はまずストーリー進行に必要なアイテムの調合から挑戦し、慣れてきたら高品質・高性能なアイテム作りにじっくり取り組むと良いでしょう。
- 依頼(クエスト): シリーズを通じて、街の人々やギルドからの依頼を受けて達成する要素があります。多くは「〇〇を○個納品してほしい」「△△というモンスターを倒してほしい」といった内容で、達成するとお金や報酬アイテムがもらえます。依頼はゲーム進行の助けになるほか、街の評判が上がったり仲間との好感度イベントが発生したりとメリットがあります。作品によっては期間限定の依頼もあり、受注と達成に期限がある場合もあります。初心者の方は無理のない範囲で依頼をこなしていくと、結果的に多くの素材や経験値が得られゲームを円滑に進められます。
- 戦闘: フィールド探索中に遭遇する敵モンスターとの戦闘は、基本的にコマンド選択式のターン制バトルです。最大3人程度のパーティを編成し、通常攻撃やスキル、そして錬金術で作ったアイテムを駆使して戦います。アトリエシリーズでは攻撃アイテム(爆弾・攻撃瓶等)や補助アイテム(回復薬・バフ道具等)が非常に強力で、調合したアイテムの出来が戦闘の難易度を左右します。そのため他のRPGに比べ、戦闘と調合が密接に関わっているのが特徴です。作品が新しくなるほど戦闘システムも洗練されており、素早さで行動順が変わるコストターンバトルや、リアルタイムに近いシームレスバトル、位置取り要素など様々な工夫が加わっています。初心者の方は弱点に合わせたアイテムを用意しておくことで難所も突破しやすくなるでしょう。
- 時間管理と期限: 初期のアトリエ作品ではゲーム内の日数経過が重要なファクターでした。調合や移動に日数がかかり、限られた期限内(例えば「3年以内」など)にゲームの目的を達成しないとバッドエンドになることもあります。このタイムマネジメント要素がシリーズの緊張感でもありましたが、人によっては難しく感じる点でもありました。近年の作品では時間制限が緩和・撤廃される傾向にあり、不思議シリーズのソフィー以降やライザシリーズでは基本的に期限を気にせずプレイできます。初心者の方はまず期限のない作品から始めるとゆったり楽しめるでしょう(※なお、2023年発売の『マリーのアトリエ Remake』ではオリジナルの5年期限モードに加え、期限なしで遊べるモードも選択可能になっています)。
以上がシリーズ共通の基礎要素です。まとめると、「街で依頼を受けて冒険に出て素材を集め、アトリエで調合してアイテムを作り、それを使ってまた冒険…」という調合と冒険のサイクルがアトリエシリーズの醍醐味と言えます。
登場キャラクターの関係と再登場
各シリーズ内では、主人公や仲間キャラクターが続編に再登場して物語に関わることがよくあります。初心者の方が混乱しやすいポイントでもあるので、代表的な例をシリーズ別に簡単に紹介します。
- ザールブルグ&グラムナートシリーズ: マリーとエリーは先述の通り師弟関係で、エリーの物語にはマリーが先輩錬金術士として登場します。リリーは時間軸的に2人より前の時代のため直接の絡みはありませんが、同じサルブルグを舞台とする歴史上の人物として位置付けられます。グラムナートシリーズは世界観を共有しており、ザールブルグシリーズの人物がユーディー(Judie)やヴィオラートの世界にゲスト出演している例があります(例えばザールブルグの名物鍛冶屋ハゲルが登場するなど)。とはいえ物語上の繋がりは薄いので、気にしすぎなくても大丈夫です。
- アーランドシリーズ: 3部作を通してロロナ→トトリ→メルルと師弟関係が受け継がれています。『トトリのアトリエ』では大人に成長したロロナがトトリの師匠として登場し、共に旅をすることもできます。『メルルのアトリエ』ではトトリがメルルの先生となり、ロロナも物語に深く関わります。このように前作主人公たちが頼れる先輩キャラになるのがアーランドの魅力です。また『ルルアのアトリエ』ではロロナが主人公ルルアの母親であり、トトリやメルル含め往年のキャラが多く再登場します。シリーズを通してプレイすると、キャラクターたちの人生の歩みを感じられるでしょう。
- 黄昏シリーズ: こちらも時間の流れが連続しているため、エスカ&ロジー→シャリーで主要キャラの再登場があります。エスカとロジーの二人は『シャリー』で大人になった姿を見せ、物語に協力者として参加します(PS3版ではエンディングに顔見せ程度でしたが、Vita版Plusでは正式に仲間に加わります)。またアーシャの物語に登場した調査員マリオンは、『エスカ&ロジー』では二人の上司として再登場し、さらに『シャリー』にも引き続き登場します。このように前作の脇役が次作で重要なポジションを担うこともあり、黄昏シリーズ3部作は一つの大河ドラマのような繋がりがあります。
- 不思議シリーズ: ソフィー、フィリス、リディー&スールの3作品でキャラクターが広がりつつ繋がっています。ソフィーとその師匠プラフタは『フィリス』にて主人公の師匠役として登場し、旅立つフィリスにテント(携帯アトリエ)を託します。さらに『リディー&スール』では、ソフィー&プラフタ、フィリス&リアーネ姉妹が首都メルヴェイユに集い、若い双子を導く大先輩錬金術士として再登場します。特にソフィーはシリーズ全体で活躍し続けているため、“ソフィーの成長物語”という視点でも楽しめます。ソフィーの直接の続編である『ソフィー2』は夢幻世界の物語で他作品キャラとの絡みはありませんが、逆にソフィー自身の物語を深掘りする内容になっています。
- ライザ(秘密)シリーズ: こちらは三部作すべて同一の主人公&メインキャラクターで物語が紡がれる異例のシリーズです。ライザを中心に、幼なじみのレントとタオ、お嬢様クラウディアなど主要メンバーは毎回登場し(新たな仲間も増えます)、彼らが成長していく様子を追体験できます。例えばタオは1作目では気弱な本好き少年でしたが、3作目では立派な青年学者に成長しています。こうしたキャラクターの成長劇を連続ドラマのように楽しめるのがライザシリーズ最大の魅力です。三部作完結済みの現在、新規プレイヤーはぜひ1作目から順にプレイしてライザ達の冒険の軌跡を辿ってみてください。
以上のように、アトリエシリーズでは**「前作であの人がこんな立場に…!」という再会の楽しみが各所にあります。ただし基本的に各シリーズ内に留まるので、世界観の異なるシリーズ間で同一人物が登場することはありません(※例外的に、シリーズ20周年記念のスピンオフ『ネルケと伝説の錬金術士たち』では歴代キャラが異世界で大集合しましたが、これはファン向けのお祭り作品です)。なお、毎回「パメラ」という幽霊娘がどこかに登場する**など、小ネタ的な共通キャラも存在しますが、初心者のうちは気にしなくて大丈夫です。
初心者におすすめの作品とプレイ順ナビゲーション
作品数が多いアトリエシリーズですが、どれから始めるか悩んだら以下の観点で選んでみましょう。プレイヤーの好みや重視ポイント別に、初心者に向いたタイトルをいくつか紹介します。また、やらなくても支障のない(後から余裕があれば挑戦したい)作品も合わせて触れます。
ストーリー重視で楽しみたいなら
⇒黄昏シリーズ(アーシャ/エスカ&ロジー/シャリー)がおすすめ。
ファンタジー世界の終末という大きなテーマがあり、キャラクターの心情描写や物語の起伏がしっかりしています。特に『アーシャのアトリエ』は主人公の健気さや旅情あふれる雰囲気が評価されており、『シャリーのアトリエ』までプレイすると世界の謎が解明されて達成感があります。時間制限は多少ありますが厳しすぎず、ストーリーを追うことが目的なら問題なく楽しめるでしょう。
⇒ライザのアトリエ(秘密シリーズ)もストーリー性◎。
ライザ三部作は主人公たちの成長ドラマが魅力で、1作目から順番にプレイするとキャラクターに強い愛着が湧きます。世界の命運をかけたシリアスさというよりは、青春冒険譚として没入できる物語です。特にキャラクター同士の関係性や成長物語を重視する方に向いています。ゲーム的にも新しいため遊びやすく、グラフィックも美麗なので感情移入しやすいでしょう。
(補足:イリスシリーズも物語重視のRPGですが、他のアトリエと毛色が異なるため、まずは上記を推します。イリスは純粋なJRPGが好きな方やシリーズに慣れてからの番外編的位置づけです)。
調合システムをとことん楽しみたいなら
⇒不思議シリーズ(ソフィー/フィリス/リディー&スール)がイチ押し。
不思議シリーズの各作品は毎回調合システムに独自の工夫が凝らされています。ソフィーのパズル調合、フィリスのオープンワールド×調合、リディー&スールの絵画世界調合など、錬金術で工夫する手応えが味わえます。時間制限も基本ないので腰を据えてレシピ探索や高性能アイテム作りに没頭できます。中でも**『ソフィーのアトリエ2』**はシリーズの集大成的な遊びやすさ・調合の奥深さがあり、調合好きなら是非プレイしてほしい逸品です(ソフィー1未経験でも問題なく楽しめます)。
⇒アーランドシリーズ(ロロナ/トトリ/メルル)もおすすめ。
アーランドの三作品は伝統的な調合+時間管理によるやりくりが光ります。特に『メルルのアトリエ』は国作り要素も加わり、限られた期間で調合と依頼を効率よく回すシミュレーション的なおもしろさがあります。各作品ともエンディング分岐があり、作れるアイテムや達成度によってマルチエンディングになるため、調合を極めるモチベーションになります。DX版で遊びやすくなっているので、昔ながらの調合ゲームを楽しみたい方に向いています。
(補足:よりハードな調合・経営を求めるなら初期ザールブルグシリーズですが、難易度が高めなのでシリーズに慣れてから挑戦すると良いでしょう。初代『マリーのアトリエ』はリメイク版でかなり遊びやすく調整されているので、興味があればそちらから体験するのも◎です)。
テンポ良くサクサク遊びたいなら
⇒ライザシリーズが最適です。
ロード時間の短縮やシームレスな戦闘移行、移動の快適さなど、現代的なゲームデザインでストレスフリーに遊べます。調合も難解すぎず直感的で、素材集めもマップ上の採取ポイントを走り回るだけで気持ちいいほど集まります。戦闘も従来のコマンド式にアクション性が加わりスピーディです。シリーズ入門として人気が高いのも納得の遊びやすさなので、「ゲームのテンポやUIを重視する」という方にはまずライザをおすすめします。
⇒ソフィーのアトリエ(1作目)も初心者向け。
ソフィーは時間制限がなく、チュートリアルも丁寧で、シリーズの基本をじっくり学べる構成になっています。ゲーム内で何をして良いか迷った時はプラフタの本が優しくヒントをくれるなど、初心者への導線がしっかりしています。難易度も低めなのでサクサク進められ、疲れず遊べるでしょう。ソフィーでシリーズの雰囲気が掴めたら、次にフィリスやリディー&スール、あるいは他シリーズに進むといったステップがおすすめです。
最新のゲームから始めたいなら
⇒『ユミアのアトリエ』に挑戦するのもアリ。
最新作ユミアはシリーズ未経験者にも配慮された設計がなされていると公式発表されています。過去作との繋がりもなく完全新規の世界なので、ここから入るのも良いでしょう。ただし発売直後で情報が少なく攻略の手引きも整っていないため、不安な場合は直近のライザのアトリエ(グラフィックやシステムに共通点が多い)を先にプレイしてみるのも手です。
やらなくても支障ない作品は?
上記で触れなかったイリスシリーズや外伝的作品は、アトリエの本流とは少し異なるため最初はスキップして問題ありません。イリス三部作(PS2作品)は戦闘重視で調合要素が簡易的なので、「普通のJRPGがやりたい」という場合にのみ検討しましょう。マナケミアシリーズも学園物のスピンオフ的位置づけで、本編と直接関係しません。こちらは男性主人公である点やターン制バトルの完成度が魅力なので、シリーズに慣れてからプレイすると新鮮に感じられるでしょう。
また、ニンテンドーDSで展開された**DSオリジナルシリーズ(リーナやアニーなど)**もありますが、現在入手しづらく、本編との繋がりもないため無理にプレイする必要はありません。どうしても興味が出たら後からレトロゲームとして楽しむくらいでOKです。
最後に、アトリエシリーズは一作ごとの完結性が高く、基本的には「このタイトルが気になる!」と思ったものから始めて問題ありません。例えば絵柄や主人公の雰囲気で選んでも大丈夫です。それぞれに魅力がありますので、自分の好みに合いそうな世界に飛び込んでみてください。錬金術士たちの世界へようこそ、きっとお気に入りのアトリエが見つかるはずです!
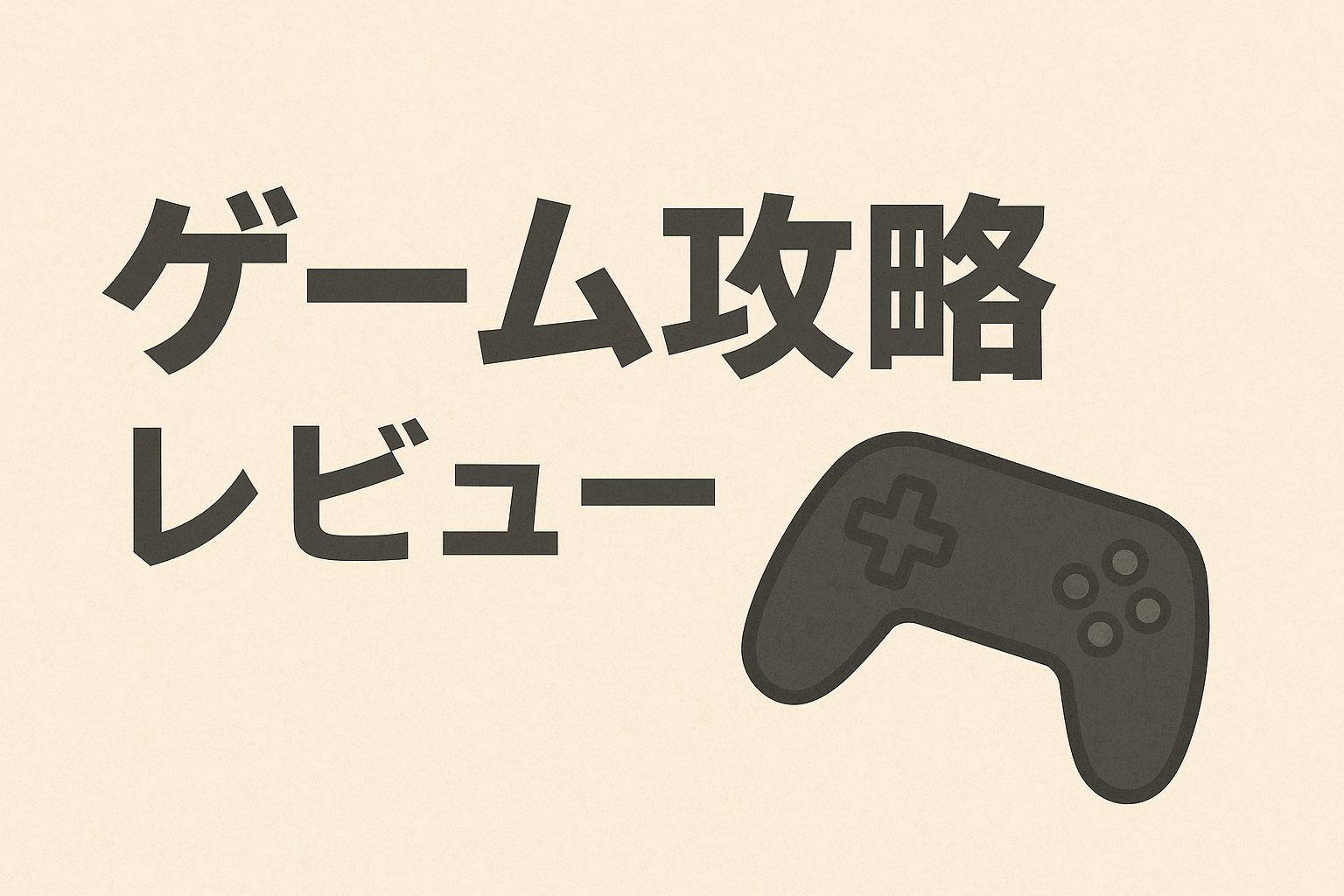
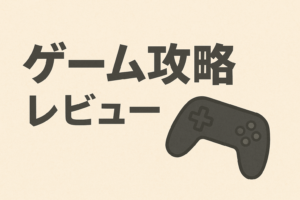
コメント